「宇宙ってなに?」
そう思ったことはないですか?
これまでもその時代の天才たちが、
この宇宙という謎に挑み、研究し、解き明かし、
世間から逆風や差別を受けながらも、少しずつ解明してきました。
まずはその歴史を知りたいと思い、勉強してみました。
✅今回の参考書籍はこちら!
「宇宙創成」サイモン・シン著
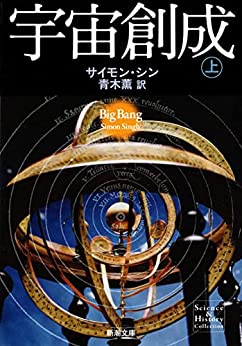
✅著者の紹介
サイモン・シンさん
「サイエンス」と「ヒストリー」を組み合わせて、数々の天才たちの人類の謎への挑戦、それに対する苦悩や栄光をおもしろくストーリーにまとめてくれるすごい人。
他の書籍「フェルマーの最終定理」なども有名です。
✅この本のザックリ内容
・現在の宇宙論(ビッグバン・モデル)
・宇宙はいつ、どのように始まったのか?
・人類永遠の謎である宇宙に挑んだ天才たち。
・宇宙解明までのエピソードと人間ドラマ。
「宇宙」の謎は、誰か一人が解き明かしたというわけではなく、ある人が疑問に思い、その後ある人が研究し、その後またある人が証明していくという、天才たちのバトンリレーで少しずつ明かされてきたのです!
✅この記事でわかること
・現代の宇宙の認識
・宇宙の謎に挑んだ天才たちの考え
・人類が宇宙についてどう考えてきたのか
✅前提の共有
では現在、宇宙についてどこまでわかっているのでしょう?
無 > ビックバン > 宇宙誕生 > 天の川銀河 > 太陽系 > 地球
ざっくりこんな感じです。
この記事では、宇宙がどのようにできたのか?
という科学的なことよりは、
「宇宙ってどうなってるんだろ」について、
人類が「どのように考えてきたのか」という歴史を中心に書いていきます。
それでは見ていきましょう!

1.神がこの世界を作った
めっちゃ昔の人たちは、当然、この地球や宇宙が、
どのようにできたのか、全くわかりませんでした。
そして、わからないことはとりあえず
「神」が作ったということにしてました。
「この世界は神が棒でかき混ぜて作った」
とか
「この大陸は怪物が横たわってできたもの」
とかですね。
この発想の方がおもしろいですよね。
また、世界は一直線で「平たん」とも思われていました。
海の向こうの端っこは海水バシャーみたいな。
落ちた海水を神がすくって、空から雨として降らす。的な。
とにかく、最初は何もわかってなかったので、すべてが人間の妄想でした。
2.ここ、丸いんじゃね?
紀元前6世紀頃、ギリシャの哲学者や科学者が考えはじめます。
「神が作ったとか、怪物とか、それちょっとちがくね?」
そして「観測」や「数学」を使って、
地球や宇宙の謎を解き明かすことをはじめます。
ある人が言いました。
「月って丸やん?太陽も丸いやん?ってことは、地球も丸い可能性あるよな?」
「たしかに、船が海の向こうに進むと、水平線に沈んでいくし、空とか海見ると、なんか球体っぽいもんな」
「ここ、丸いんじゃね?」
さらに、この時代に頭の良い人が数学の知識を使って、地球・太陽・月の距離や大きさも計算してしまったようです。
このころ活躍したのが「ピタゴラス」や「アリストテレス」です。
聞いたことはある気がしますよね。
この時点で、地球が丸いこともわかり、太陽や月との距離もわかり、大きさまでわかってしまいました。
まじ天才すぎ!
しかし、1つ大きな誤解がありました。
「すべての天体は、地球を中心に回っている」
「天動説」ってやつですね。
地球は動かず、中心にあって、地球の周りを星が回っているという考えです。
なぜそう思ったかというと、
ある人は言いました。
「周りの星は動いてるけど、ここ動いてなくない?」
「てか、地球動いたら、おれら立ってられなくない?」
「地球動いてたら、向かい風ビュンビュン来るやろ」
「絶対動いてない。はい、地球は完全に止まってます」
これが当時の人の認識でした。
そう考える方が「自分たちは宇宙の中心にいる」という感じで、
自己肯定感に包まれていたんでしょうね。
そして、宇宙と人類の戦いはここからが本番でした。
3.古代の人たちを「惑わせた星」
「惑星」という言葉の由来を考えたことはありますか?
実は「惑星」とは、古代ギリシャ人を惑わせていた星ということで名付けられたらしいです。
なにを惑わせていたのか?
それが「惑星の逆行」です。
地球を中心にすべての天体は回っているという考えだと、この「惑星の逆行」が説明できなかったのです。
※惑星の逆行については割愛しますが、簡単に言うと、星が地球中心説だとありえない動き方をしているって感じです。
そこで、プトレマイオスという人がつじつま合わせのような論文を出して、無理矢理でも地球中心説に都合を合わせるために考えていました。
そんな中、アリスタルコスという人が言います。
「もしかして、本当は太陽中心なんじゃないすか?」
しかし、この発言は1500年くらい無視されます。
だれも理解してくれなかったのです。
さすがに可哀想すぎますよね。
2,3日無視されるのもつらいのに、1500年無視されるって…絶望
4.太陽が中心なんだよ!信じてくれよ…
16世紀になってようやく、
コペルニクスという人が言います。
「太陽中心じゃん!!」
これを証明したいコペルニクスはがんばります。
いろいろ調べて研究して、「太陽が中心だ」という内容の本を出版します。
しかし、全く売れませんでした。
その原因としては、
①コペルニクスがまだ何の実績もない無名だったので、だれも信用していなかったこと。
②本の内容が難しすぎて、全然興味を持たれなかったこと。
③「太陽中心」を証明する計算の精度が低かったこと。
でした。
「太陽中心」という証明が完璧にできれば、無名でも説得力が増すのですが、
星の軌道について、計算が合わない箇所があったのです。
その原因として、その時代に勘違いされていたことがありました。
「星の公転の軌道は、完璧な円」
これは、あの天才「アリストテレス」が言ったことでした。
アリストテレスが偉大すぎるあまり、
この人が「星の軌道は美しい完全円だ」と言ったら、
そのことを疑う人はいませんでした。
これが1000年以上も信じられてしまったのです。
5.もしや楕円じゃね?
それからしばらく経って、コペルニクスの「太陽中心説」の本を読んだ
ケプラーという人が言いました。
「太陽中心説か…おもしろいな。でも計算が合わないのか…ん~…」
「あれ?星の進むスピードは一定じゃなく、早いときと遅いときがあるぞ!」
「もしかして、星の軌道はきれいな円じゃなくて、ちょっと潰れた楕円形なんじゃね!?
それなら計算が合うぞ!!」
これが大正解でした。
この発見が宇宙の謎をさらに解明します。
6.望遠鏡による躍進
17世紀になると、ある天才が現れます。
ガリレオ・ガリレイです。
さすがに聞いたことはありますよね。
ここから、【ガリレオvs天動説】の戦いがはじまります。
ガリレオは一貫して地動説を唱えます。
「地球は宇宙の中心ではない!地球も動いているんだ!」
ガリレオはそれを証明するため、その時代最強の望遠鏡を自作します。
その最強望遠鏡で地球も動いていることを証明していきます。
・木星にも衛星があることを発見!
→すべての星が地球を回っているわけではない。
つまり地球が中心とは言えない。
・太陽に黒点や月にクレータを発見!
→星は綺麗な丸ではない
軌道も綺麗な円ではない可能性あり
・金星に満ち欠け
→地球中心ならありえない
太陽中心じゃん!
数々の発見をしたのち、本を出版!
しかし、教会から反感を買い、撤回されてしまいます。
ガリレオは裁判にかけられ敗北。
裁判所を立ち去るときに放った名言がこちら。
「それでも地球は動いている」
しびれる〜
7.宇宙にはじまりはあるのか
20世紀になると天動説を信じていた人が引退していき、教会も世間も地動説を理解していきました。
そしてここにきて、ある疑問が浮上します。
「ところで、宇宙ってどうやってはじまったの?」
それまでは、神が棒でかき混ぜて作ったことになっていました。
さすがにそれはもうええて。
というわけで、また新たな対立。
「宇宙は永遠の過去から存在している」
vs
「宇宙はある時点から創成された」
8.相対性理論
ここで登場したのが、
ガチ天才のアインシュタイン先生です。
アインシュタインは、特殊相対性理論や一般相対性理論という、一夜漬けでは理解できないものを発表しました。
めちゃくちゃ要約
・一般相対性理論:重力が時間や空間を曲げる
・特殊相対性理論:物体が光の速度に近づくと、時間や空間が変わってしまう
つまり、時間も空間も伸び縮みするから、重力が空間をゆがめる
ということです。
ちょっとわけわからんちゃんですね。
ここはなんとなくで大丈夫です。
アインシュタインはこの理論から、
「強大な重力によって、宇宙が伸縮しているかも!」
ということを導き、
「宇宙は伸縮しているけど、大きさは一定だ」
だという「宇宙定数説」を結論としました。
9.ビックバン成立!
その後、フリードマンとルメートルという人が言いました。
「アインシュタインの宇宙定数って無茶じゃね?」
「宇宙は伸縮ではなく、膨張してるんじゃね?」
→「宇宙膨張説」
「だから、もともとは小さかったはず」
「小さかった何かからビックバンが起きて、今も膨張しているんじゃね?」
これはあくまでも、
フリードマンとルメートルの想像でした。
そして、1923年にそれが証明されます。
まずはじめの疑問は、
「地球がいる天の川銀河って宇宙で唯一の銀河ですか?」
ということでした。
この疑問は、ハッブルという人によって解明されます。
ハッブルの観測によって、めちゃくちゃ遠い天体の観測に成功し、
「この星、天の川銀河のものじゃありません!」
「宇宙に銀河めちゃくちゃいっぱいあります!宇宙は銀河だらけです!」
となります。
さらに、
「他の銀河を観察してみると、少しずつ遠ざかってます!」
「宇宙は膨張してます!」
となり、現在も宇宙は光よりも速いスピードで膨張し続けていると言われています。
そうなると最後に証明したいのは、
「本当にビックバンが起きていたのか」ですね。
そして、1940年
ガモフ、アルファ、ハーマン(あまり聞いたことのない方々)が宣言します。
「『光のこだま』と呼ばれる、『ビックバンが起きたときの光の名残』を見つければ、
ビックバンが起きたかどうかがわかる!」
そして、1992 年にCOBE衛星が『光のこだま』宇宙で発見して、
「ビックバンは起きていた」
という証明がされました!
まとめ
いかがだったでしょうか?
最後は巻き巻きに巻いてしまいましたが、
宇宙の謎はつい最近までに、いろんなことが解明されており、
まだまだ謎は多いと言われています。
現在まできてようやく、
宇宙が「無」から「ビックバン」が起きて生まれた
ということが解明されました。
そしてここまでには数多くの天才たちが苦悩と逆境を乗り越え、
バトンを繋いできたからこそ辿り着いたと言えます。
天才たちが挑んできた人類最大の謎は、
まだ完璧には解明されていません。
これから解明していく、
つまり、天才たちのバトンを次に受け取るのは、
あなたかもしれません。
今回は以上です。
ではまた!



コメント